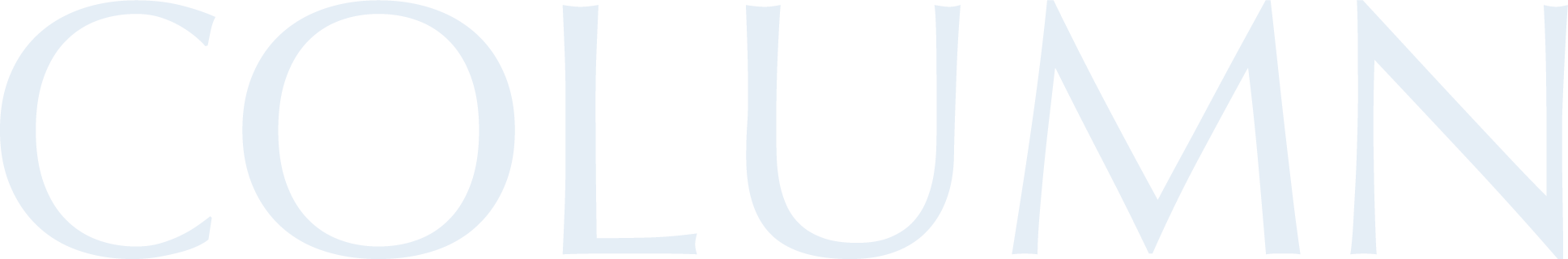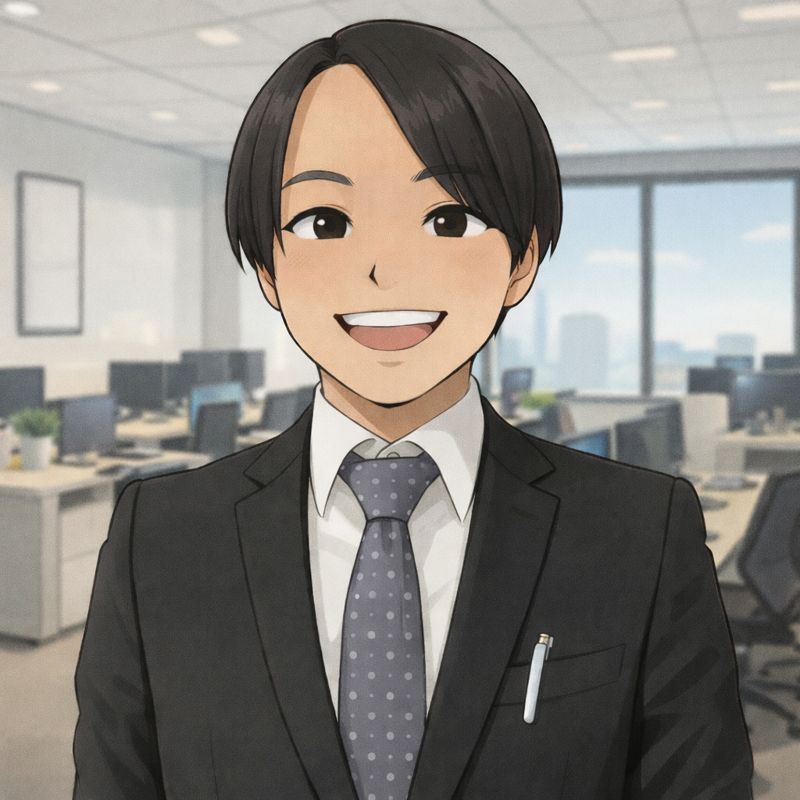【2025年最新】ホテル・旅館のインバウンド対策は何から始める?集客から受け入れ体制まで網羅

近年、訪日外国人観光客の数が急速に回復し、インバウンド需要の波が再び日本の宿泊業界に押し寄せています。中小規模のホテルや旅館にとって、インバウンド対策は売上拡大の有効な手段である一方で、文化や言語の違いによる対応の難しさという課題もあります。
この記事では、最新のインバウンド動向を踏まえた集客方法から、受け入れ体制の整備、さらに活用できる補助金やプロの支援サービスまでを徹底解説。訪日外国人の満足度を高め、安定的な売上確保を目指すために、今、どのような準備が必要なのかをわかりやすくご紹介します。
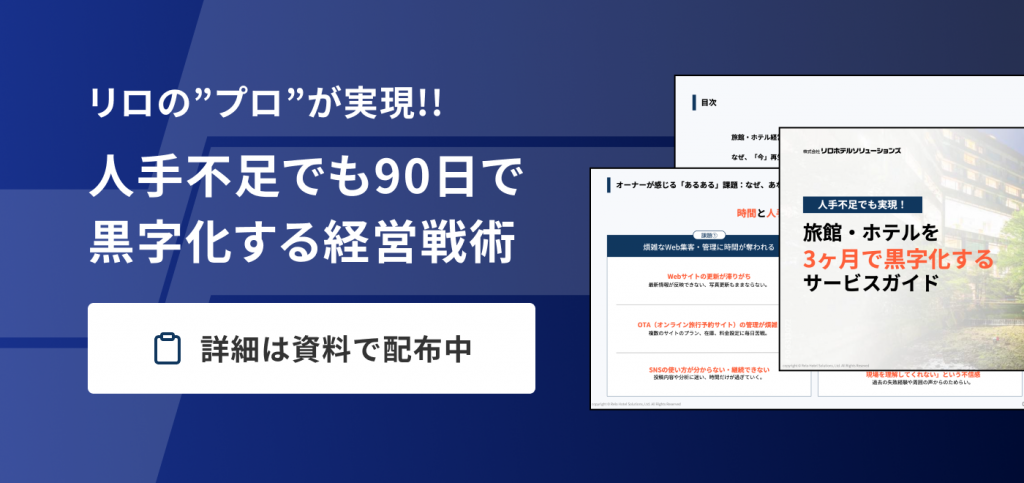
急回復するインバウンド需要!宿泊業界の現状とは?
近年、日本政府は「観光立国推進基本計画(2023〜2025年度)」を策定しました。2025年までに訪日外国人旅行者数を「2019年水準(3,188万人)越え」、旅行消費額を「5兆円以上」にする目標を掲げています。具体的なインバウンド対策として、ビザの戦略的緩和やキャッシュレス化、デジタルマーケティングを活用した訪日プロモーションの実施などを推進中です。
実際コロナ禍で激減した観光客数は、その後2023〜2024年に急回復し、2024年は約3,687万人、消費額は8兆円超と、上述した目標値を早々に達成。2025年に入ってからも勢いは衰えず、4月・5月と好調を維持。6月は約338万人で6月では過去最高の月間数値を更新し、順調にその数を伸ばしています。
こうした量的回復に加え、近年は「量」から「質」へとトレンドが移行。中小規模のホテルや旅館では、リピーターや地方体験を重視するインバウンド視点が求められています。今後は単に数を追うだけでなく、宿泊客一人ひとりの満足度向上、地域との共生を意識した質重視の経営が重要となるでしょう。
参照:
インバウンド対策がもたらす3つのメリット
インバウンド需要を取り込むことは、ホテル単体の利益だけでなく、地域経済やブランド価値の向上にもつながります。ここでは、インバウンド対策がもたらす代表的な3つのメリットを紹介します。
- 売上の拡大
- 稼働率と客単価の向上
- 地域の活性化とブランド向上
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
売上の拡大
少子高齢化が進み、国内の旅行市場は今後縮小が懸念されています。こうした中で、インバウンドは新たな需要の獲得手段として、大きな可能性を秘めています。
訪日外国人観光客は、宿泊・食事・体験型サービスなどへの消費意欲が高く、長期滞在やリピーター化が進めば、安定した売上源として期待できます。季節や曜日に左右されにくく、イベントや観光資源と組み合わせることで客単価が上がりやすい点も魅力です。
国内需要が頭打ちになりつつある今こそ、海外顧客を視野に入れた販路拡大が、ホテルの持続的な成長につながるでしょう。
稼働率と客単価の向上
インバウンド対策を進めれば、特に平日や閑散期の稼働率向上が期待できます。訪日観光客の行動パターンは、ビジネスや長期滞在を目的とした需要も多く、必ずしも週末や連休に集中しないためです。
さらに、外国人旅行者の中には「日本ならではの体験」や「快適な滞在」を重視する層も多く、高付加価値なサービスの提供が受け入れられやすい傾向があります。
たとえば、和風の客室アレンジや通訳付きの文化体験、グルテンフリーやヴィーガン対応の食事などは、価格競争に巻き込まれずに客単価を上げる有効な施策です。
地域の活性化とブランド向上
インバウンド誘致は、ホテルだけでなく、地域全体の魅力を高めるチャンスにもなります。宿泊者が地域の観光資源や飲食店、交通機関を利用すれば、周辺の経済波及効果が広がるでしょう。
また、SNSや口コミサイトを通じて地域の魅力が世界に発信され、ブランド価値の向上にもつながります。地元ならではの祭りや伝統文化体験、特産品を活かした滞在プランなどを提供することで、「ここでしか味わえない旅」が実現でき、結果的に地域のファンづくりにも貢献できるでしょう。
インバウンド対策で知っておくべき課題
インバウンド対策には多くのメリットがある一方で、課題も無視できません。対応コストや文化の違い、既存顧客とのバランスなど、事前に押さえておくべきポイントを整理しておきましょう。
- 対応コストが増える
- 文化や習慣に由来するリスクがある
- 既存顧客への配慮が必要
順に見ていきましょう。
対応コストが増える
インバウンド対策を実施するにあたり、最初に直面するのがコスト面の課題です。たとえば、多言語対応のWebサイト構築やキャッシュレス決済の導入、館内Wi-Fiの整備などは、いずれも初期投資と継続的な運用コストがかかります。
また、外国語対応ができるスタッフの教育や、新たな人材の雇用も検討が必要です。さらに、異文化理解や接遇マナーの研修にも時間と手間がかかるため、現場の負担も大きくなりがちです。
こうした背景から、最近では公的補助金の活用が有効です。「IT導入補助金」や「インバウンド対応力強化支援補助金」などを活用することで、システム整備や多言語化にかかる経費の一部を軽減できます。
予算面で不安がある場合は、自治体や専門機関に相談することも選択肢の一つです。
文化や習慣に由来するリスクがある
インバウンド対応では、文化や習慣の違いによるリスクにも注意が必要です。たとえば、チェックインの時にイスラム圏からのお客様に「メッカの方角はどちらですか?」と尋ねられ、スタッフがその場で慌てて調べたという事例があります。これは、イスラム教徒が一日に数回、メッカの方角に向かって礼拝を行うという習慣を知らなかったために起きたケースです。スタッフが事前にイスラム圏に関する基本的な文化知識を持っていれば、スムーズに対処できたケースといえるでしょう。
このような、文化や習慣に由来するリスクに対応するためにも、多文化理解を深める研修やマニュアル整備が求められます。
既存顧客への配慮が必要
インバウンド対応に力を入れるあまり、従来からの日本人顧客へのサービス品質が低下してしまうケースも少なくありません。たとえば、外国語対応に追われることで、チェックイン時の対応が遅れたり、客室案内に手間取ったりする場合が考えられます。
結果的に、常連客や国内の旅行者が不満を感じてしまっては本末転倒です。重要なのは、インバウンドと既存顧客の両方にとって心地よいバランスを保つ体制づくりです。
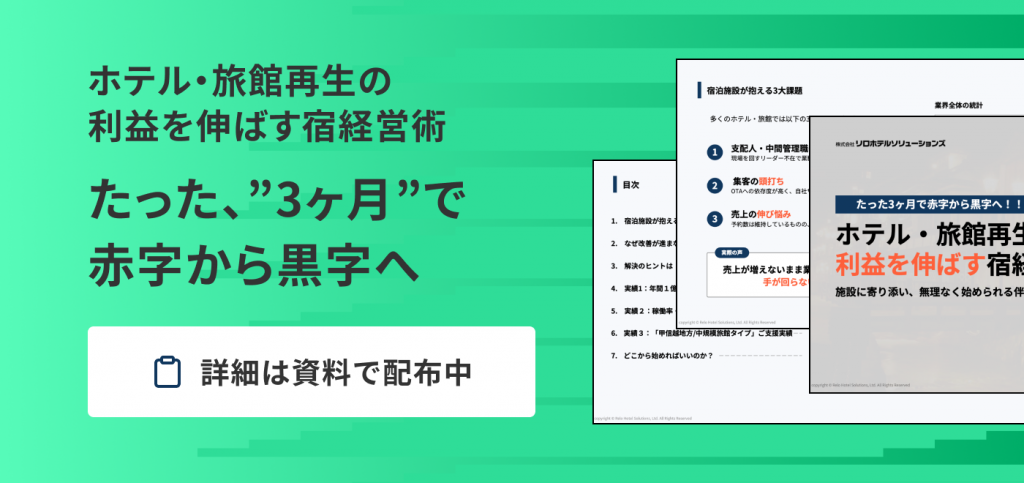
【集客編】旅行前の訪日外国人に選ばれるための対策
宿泊先の選定は、訪日前の情報収集の段階でほぼ決まります。インバウンド集客を成功させるためには、WebやSNS、OTA(オンライン旅行代理店)などのオンライン上で「選ばれる工夫」が欠かせません。
主な対策は次の3点です。
- Webサイト・予約システムの多言語対応
- 海外OTAとSNSの効果的な活用
- MEO・SEO対策
順に解説します。
Webサイト・予約システムの多言語対応
訪日外国人にとって、ホテルの公式Webサイトは最初の情報接点です。
特にターゲットとする国や地域の言語でコンテンツを整備し、「何が魅力なのか」「どうアクセスすればよいか」「どんな設備があるか」などを明確に伝える必要があります。
また、見落とされがちなのが予約のプロセスです。フォームが英語対応していなかったり、決済方法に制限があったりすると、途中で離脱される恐れがあるでしょう。
そのため、多言語対応のオンライン予約システムを導入し、予約から決済までをスムーズに完結できる環境を整えることが、集客の基本であり最優先の対策といえるでしょう。
海外OTAとSNSの効果的な活用
訪日外国人の多くは、旅行計画の段階で海外OTA(オンライン旅行代理店)を利用しています。Booking.com、Agoda、Expediaなどに登録すれば、世界中からの集客を増やすチャンスです。
また、SNSは訪日前のイメージ形成において重要な役割を担います。特にInstagramやFacebookでは、美しい写真や動画によってホテルの雰囲気や周辺環境を視覚的に伝えることができます。
ハッシュタグも戦略的に活用しましょう。「#JapanTravel」「#TokyoHotel」など英語圏ユーザーが検索しやすいタグを設定すれば、検索結果に表示されやすくなります。
OTAとSNSを組み合わせることで、ブランディングと予約獲得の両方を効果的に進めることができるでしょう。
MEO・SEO対策
訪日外国人の多くが、Googleマップを使って宿泊施設を探す現在、MEO(マップエンジン最適化)は欠かせません。まずはGoogleビジネスプロフィールを整備し、営業時間や住所、支払い方法などの基本情報を多言語で掲載しましょう。写真や施設の外観・内観のイメージも重要です。
さらに、口コミに対して多言語で丁寧に返信すれば、信頼性のある施設として評価されやすくなります。
一方、SEO対策も同様に重要です。検索エンジンで「Tokyo hotel with vegan breakfast」などの具体的な検索に対応できるよう、外国人が使いそうな英語キーワードをページ内に自然に盛り込むことが集客の鍵となります。
検索エンジンと地図アプリの両方で「見つけてもらえる」仕組みづくりが重要です。
【受け入れ体制編】滞在中の満足度を高め、良い口コミに繋げるおもてなし
訪日前の集客だけでなく、滞在中の快適な体験こそが、リピーター獲得や高評価レビューの鍵となります。安心・安全で心地よい滞在を提供するための体制整備が重要です。
スタッフ・施設の多言語対応
多言語対応は、訪日外国人に安心感を与える最初のステップです。まず、スタッフが英語や中国語などの簡単なあいさつやフレーズを習得するだけでも、ゲストに好印象を与えられます。
加えて、外国語が話せる人材の積極的な採用も有効です。しかし、すべてを人手で対応するのは難しいため、翻訳アプリやタブレット端末、多言語対応のモバイルオーダーシステムなどのツールを活用して、スムーズなやりとりを実現しましょう。
また、館内案内板やレストランのメニュー、避難経路表示などは、英語・中国語・韓国語などの主要言語で併記するのが望ましいです。
物的・人的・技術的なアプローチを組み合わせることが、多様な宿泊者への対応力を高めるポイントとなるでしょう。
決済・通信環境のグローバルスタンダード化
訪日外国人にとって、支払い方法や通信環境は、宿泊満足度に直結する要素です。特にキャッシュレス化が進む海外では、現金決済のみの施設は不便に感じられ、宿泊先の候補から外されてしまう可能性もあります。
VISAやMastercardなどの主要なクレジットカードはもちろん、Apple PayやGoogle Payといったモバイル決済への対応は、今や必須条件となっています。
また、インターネット環境も重要です。SNSでの情報発信や、家族・友人との連絡手段として、Wi-Fiは欠かせません。館内のどこでも安定して使える無料Wi-Fiを整備することで、宿泊者の満足度が高まり、良い口コミにつながるでしょう。
決済と通信環境の整備は、「快適さ」を提供するための基本インフラと考えるべきです。
食事の多様性(ダイバーシティ)への対応
食事は旅行の大きな楽しみである一方、文化や宗教、健康上の理由から制限がある人にとっては不安の種でもあります。ベジタリアンやヴィーガン、イスラム教徒向けのハラール(※)対応メニューを用意することは、宿泊施設としての信頼度を高める大きなポイントです。
※イスラム法で食べることが許されている食品や行動、考え方
すべての料理を対応させる必要はありませんが、該当するゲストに対して、事前に選択肢を提示できる体制を整えることが重要です。また、アレルギーや宗教的禁忌に配慮した表示として、ピクトグラム(※)を活用する方法も効果的です。
※「文字や言語に頼らず、絵や図で情報を伝える視覚記号」
引用元:ユニバーサルデザイン協会|「みんなのピクト」導入で、ビュッフェ会場のアレルギー表示をわかりやすく
言葉がわからなくても視覚的に内容を理解できるため、安心して食事を楽しんでいただけます。
食の多様性への配慮は、国際的なホスピタリティの基本と言えるでしょう。
災害時の情報提供と安全確保への備え
日本は、地震や台風など自然災害が多いため、宿泊中の安全確保も欠かせません。まず、災害時の避難誘導については、多言語で表記された館内案内や避難経路マップを用意することが重要です。
また、スタッフが非常時の対応方法を理解していれば、落ち着いて誘導できます。
さらに、日本政府観光局(JNTO)が提供する多言語対応アプリ「Safety tips」の活用もおすすめです。地震・津波・気象警報などの情報をリアルタイムで確認できるため、フロントなどでアプリを案内し、宿泊者にインストールを勧めることで、安心感につながるでしょう。
「安全に過ごせる」という安心感は、宿泊体験の質を大きく左右します。災害対策こそ、ホテルの信頼性を示すバロメーターです。
インバウンド対策はプロに相談しよう
インバウンド対応には、言語・文化・制度面の配慮やシステム導入など、専門的な知識と実務対応が求められます。自力だけで対応するには限界があるため、不安を感じているホテル経営者の方は、プロの力を借りるのも現実的な選択と言えるでしょう。
そこで注目したいのが、豊富な実績と全国対応力を誇る「リロホテルソリューションズ」です。リロホテルソリューションズは、宿泊施設の運営改善から収益最大化、インバウンド戦略支援までをワンストップでサポートする運営代行の専門企業です。
インバウンド対応についても、多言語対応の導入支援やOTA戦略、受け入れ体制の構築まで、包括的に支援できます。
施設ごとの状況に応じた最適な施策を提案できるため、安心して取り組みを進められるでしょう。
まとめ
インバウンド需要の回復が進む今、ホテルや旅館が訪日客を取り込むためには、集客と受け入れ体制の両面での対策が欠かせません。多言語対応や食事、災害対策など、きめ細やかな準備が顧客満足度の向上につながります。
ただし、すべてを自社でまかなうのは負担も大きいため、専門家のサポートを受けるのが現実的です。リロホテルソリューションズでは、豊富な運営ノウハウを活かし、施設ごとの課題に応じたインバウンド戦略を提案しています。
今こそ、プロの力を活用して、持続的な収益力を高めるチャンスです。まずは公式サイトからお気軽にご相談ください。
【監修者情報】
株式会社リロホテルソリューションズ
「90日で黒字化」を目標に、全国リゾート地・過疎地の宿泊施設を運営してきたプロ集団です。
あらゆる課題を抱える宿泊施設様のご支援を行い、売上の確保だけでなく、収益確保や運営効率まで一貫したご支援を行います。。